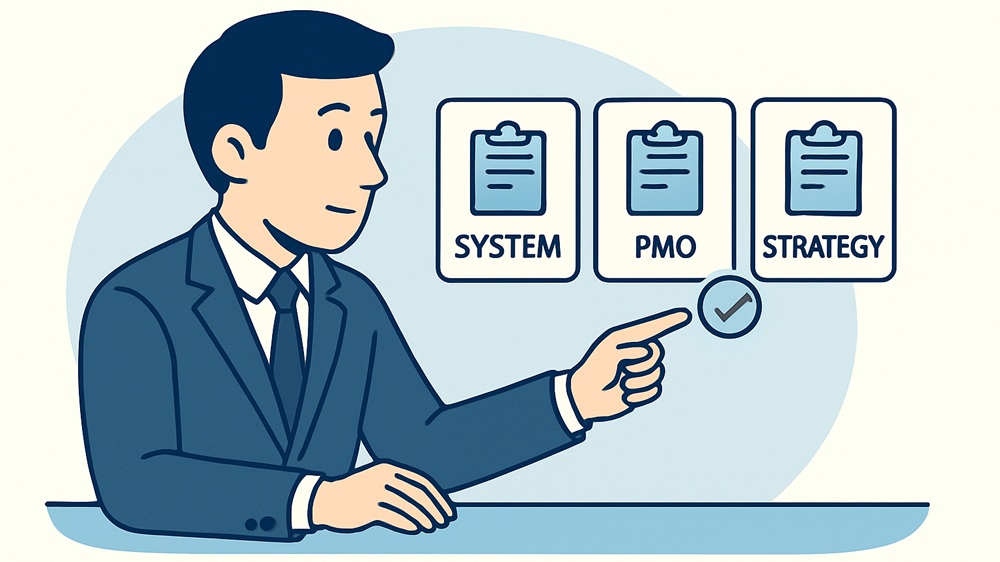コラム
ITコンサルタントの案件例まとめ:システム導入・PMO・IT戦略策定支援
ITコンサルタントの役割は、クライアント企業の経営戦略をヒアリング等により整理し、それに基づいたIT戦略、グランドデザイン、ロードマップ、投資計画を策定し、必要なツールの導入を支援することにあります。また、費用対効果やスケジュール面も考慮しながら、最適なシステムの選定・導入に向けた分析や提案も担います。このように、ITコンサルタントの業務範囲は非常に広範です。本記事では、ITコンサルタントの具体的な仕事内容について解説します。特に代表的なプロジェクト例である「システム導入」「PM・PMO支援」「IT戦略策定支援」の3種類について、それぞれ詳しく見ていきます。 ITコンサルタントへの転職を検討している方や、その仕事内容をより知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
| ITコンサルタントの代表的な案件について
| システム導入
近年、コンサルティングファームが手掛ける案件の中で最も増えているのがシステム導入です。元来は上流工程(戦略策定や要件定義など)のみを担当していたファームも、現在では下流工程までワンストップで担う事例が増えてきました。背景には国策としてDX(デジタルトランスフォーメーション)推進の潮流があり、各企業が本格的に業務のデジタル化に取り組み始めていることが挙げられます。
| PM・PMO支援
PMO支援の案件への需要も高い状態が続いています。近年はクライアント企業の情報システム部門に入り込み、その立場からプロジェクト管理を支援するケースが増えています。本記事では、クライアント企業側でのPMO支援案件に焦点を当てて説明します。
| IT戦略策定支援
IT戦略支援のプロジェクトでは、IT戦略の策定やシステム導入時の構想策定といった経営に直結する超上流工程を担当します。その業務内容は多岐にわたり、例えば次のようなものが含まれます。
・経営戦略に沿ったIT戦略・グランドデザインの策定
・IT投資計画の策定
・IT活用のための組織体制の構築
・次期システム刷新に向けた構想策定
・製品・ベンダー選定に向けたRFP作成支援
プロジェクト遂行にあたっては、クライアント企業のCIO(最高情報責任者)や情報システム部門の責任者クラスと直接やり取りすることが多く、経営に与えるインパクトが大きいことから極めて重要な役割を担うプロジェクトと言えます。
以降、それぞれの案件種類ごとにさらに詳細の解説をしていきます。
| システム導入案件の特徴は?
| プロジェクトの目的
システム導入プロジェクトでは、「要件定義」から「稼働支援」までの幅広いフェーズがあります。システム導入の目的は、導入するシステムによってさまざまですが一般的には業務効率化や内部統制の強化、情報の「見える化」による経営判断の迅速化などが挙げられます。例えば、SAPをはじめとしたERPパッケージを導入する場合、グループ全体の統制強化や業務標準化、経営情報の可視化といった企業全体の最適化を図るケースが多く見られます。一方、BPMツールやRPAなどのフロント系システムの場合は、現場業務の効率化やコスト削減を目的に導入されます。
| システム導入案件が増えている背景
システム導入案件の増加要因として、まずDX推進への対応が挙げられます。DX(デジタルトランスフォーメーション)とはデジタル技術を活用して社会やビジネスそのものを変革することであり、単なる業務効率化にとどまらない大きな潮流です。2018年に経済産業省が発表した『DXレポート』では「2025年の崖」と呼ばれる問題が指摘されました。そこでは、次のような課題が挙げられています。
・既存システムの老朽化と、デジタル化の進展によるデータ量の爆発的増加
・メインフレーム人材の高齢化による担い手不足と世代交代の必要性
・先端IT人材の慢性的な不足(急速な技術進化に対して人材育成が追いついていない)
こうした問題を放置すれば、市場や技術環境の変化に柔軟に対応できず、激化する世界のデジタル競争で敗者となる危険性があると警鐘が鳴らされています。そこで、この危機を回避するために多くの企業がDX推進の一環として既存システムの見直し・最適化に着手しているのが現状です。 さらに、世界的に利用されているERP製品SAPの現行バージョンが2027年に保守サポート終了予定であることも、システム導入需要を押し上げる大きな要因です。SAPを導入している企業では、最新バージョンであるSAP S/4HANAへの切り替えが急務となっており、コンサルティングファーム各社でも関連プロジェクトの受注が急増中です。SAPの大規模導入プロジェクトは必要な人員も非常に多いため、SAPコンサルタントの人材不足も深刻で、フリーランスで働くITコンサルタントの活用も進んでおります。
| プロジェクトの概要
典型的なシステム導入プロジェクトは、「業務要件定義」「システム要件定義」「設計・開発」「移行」「初期稼働支援」という順序で進行します。基幹系システム、大規模なシステム開発系の案件では基本的にはウォーターフォール型の進め方が主流です。 プロジェクト期間は導入するシステムやプロジェクト規模によってさまざまです。例えば、パッケージ製品をカスタマイズせずそのまま適用できるケースでは、最短で半年ほどで導入が完了する場合もあります。逆に、企業の基幹となる大規模ERPシステムの刷新プロジェクトでは、2〜3年がかりの長期プロジェクトになることもあります。また、RPAやBPMといったフロント系システム導入は製品にもよりますが、おおむね3か月〜1年程度で実施されることが一般的です。 プロジェクトの体制規模も様々です。小規模なシステム導入で、かつクライアント企業側が主導して進めるような場合は、わずか数名のチームで対応できることもあります。逆に数百名規模に及ぶ大掛かりなプロジェクトでは、100〜200名のメンバーを複数のチームに分けて進行するケースも珍しくありません。どのような案件でも、初期の要件定義フェーズでは参加メンバーが比較的少なく、設計・開発・移行とフェーズが進むにつれて必要な人員が増えていきます。そして本番稼働を迎えて稼働後支援フェーズへ移行すると、徐々にチーム規模を縮小していく傾向があります。
| プロジェクトの流れと業務内容
業務内容はシステム導入の各フェーズによって異なるため、フェーズごとに主なタスクを説明します。
要件定義
要件定義フェーズは、大きく業務要件定義とシステム要件定義に分かれます。いずれの場合も、クライアントと綿密に打ち合わせを重ねながら必要な要件を洗い出し、ドキュメントに取りまとめる作業です。特にパッケージシステムの要件定義では「Fit & Gap」と呼ばれるプロセスを実施し、システムの標準機能がクライアントの業務に適合しているかどうか、実機でのデモを交えて検証していきます。
設計
設計フェーズでは、要件定義で確定した内容をもとに各種設計書を作成していきます。場合によってはクライアントと追加の打ち合わせを行い、細かな仕様を詰めていくケースもありますが、要件定義段階と比べると打ち合わせの頻度は落ち着き、ドキュメントをまとめる作業の比重が高まります。
開発
開発フェーズではシステム機能の実装(プログラミング)を行います。ただし、コンサルティングファームにおいて自社のコンサルタントが直接コーディングまで担当するケースは多くありません。実際の開発作業は海外のオフショア開発拠点や外部ベンダーに委託されることがほとんどです。したがって、コンサルタントの主な役割は、開発者とのやり取りを通じて進捗状況や課題を管理し、プロジェクトが予定通り進むよう調整することになります。
テスト
テストフェーズでは、総合テスト(SIT)とユーザー受け入れテスト(UAT)の二段階でシステムを検証します。SITでは、委託先の開発者が実装した各機能が設計通りに動作するか、システム全体を通じてテストを実施します。一方、UATではクライアント企業側(ユーザー部門や情報システム部門)の担当者が主体となり、構築されたシステムが業務要件どおりに機能するかを確認します。コンサルタントとしては問い合わせや不具合対応の窓口となり、開発者と調整しながら原因の調査やプログラム修正を進めていきます。
移行
移行フェーズでは、本番稼働に向けてデータ移行計画を策定し、実際のデータ移行作業を行います。本番直前には少なくとも2回はリハーサル(試行)移行を実施し、所要時間を計測しながら計画を最適化したり、リハーサル中に発生した課題への対策を講じたりします。なお、移行作業時の役割分担はプロジェクトや採用する移行手法によって異なるため、プロジェクトごとに適切な体制を整える必要があります。
稼働支援
稼働支援フェーズでは、システムが本番環境で稼働を開始した直後の一定期間(一般的に約3か月間)に発生するさまざまなトラブルへ対処します。具体的には、ユーザーからの問い合わせ対応、障害の原因調査と開発チームへの修正依頼、細かな仕様変更への対応などの業務が挙げられます。こうした稼働直後のサポートが完了すれば、システム運用は日常の保守体制へと移行し、ひとまずプロジェクト終了となります。
| プロジェクトの醍醐味
システム導入プロジェクトの醍醐味は、戦略立案系や非IT系の案件とは異なり、具体的なソリューションの提案・実行を通じてクライアント企業の業務改革や課題解決を直接肌で感じられる点です。導入したシステムによって業務プロセスが改善され、クライアントの現場で実際に効果が現れる様子を間近で見られるのは、大きなやりがいにつながります。 また、プロジェクト規模が大きければ大きいほど、関わる人数も増えます。100~200名規模のプロジェクトでは、多くのメンバーが一丸となって一つの目標達成に取り組むため、チーム全体の一体感を味わえるでしょう。プロジェクト完了後の打ち上げや忘年会などのイベントも大人数で行われるため、普段は接点の少ない他チームのメンバーとも交流が広がり、人脈づくりの面でも貴重な経験となります。
| PM・PMO支援案件の特徴は?
| プロジェクトの目的
クライアント企業内のプロジェクトを円滑に遂行するためにマネジメント業務を支援することです。PMOとは「Project Management Office」の略で、企業内のプロジェクトを部署横断で支援・統制する組織/バーチャル組織を指します。
これまではコンサルティングファームやSIerが受託したシステム導入プロジェクト内にPMOチームを編成し、プロジェクト管理を支援するケースが一般的でした。しかし近年では、事業会社(クライアント企業)の情報システム部門やユーザー部門に入り込み、その立場からPMO業務をサポートする案件も増えています。
| PM・PMO支援案件が増えている背景
PM・PMO支援案件が増加している背景として、大きく二つの要因が考えられます。ひとつはDX推進やSAP 2027年問題に伴う大型プロジェクトの複雑化です。基幹システムの刷新と並行してAI・RPA・BPMといったフロント系システムを新規導入するケースも増えており、複数プロジェクトの同時進行によって調整事項が格段に増えてきております。結果としてプロジェクト遂行の難易度が高まり、全体を統括・管理するPMOの役割がますます重要になってきています。もうひとつは、クライアント企業側の人員不足です。多くの企業の情報システム部門ではIT人材が不足しており、自社だけでは大規模プロジェクトの人手を賄いきれず、一時的に外部のPMO人材を補強したいというニーズが高まっています。このような理由から、専門知識を持ったPMOコンサルタントを外部から招へいする需要が増えているのです。
| プロジェクトの概要
PM・PMO支援が必要となるのは主に大型プロジェクトであるため、プロジェクト全体の期間は1~3年に及ぶケースが多く見られます。ただしPMO支援自体はクライアント企業の情報システム部門などにスタッフを増員・補充する位置づけであるため、契約上は3か月単位で更新する形を取るのが一般的です。
| PMOコンサルタントの仕事内容
PMOコンサルタントはプロジェクトマネージャー(PM)の補佐役として、プロジェクトの品質管理・納期管理、要員計画やコスト管理、全体進行の統制など多岐にわたる業務を担います。進行中のリスクをいち早く発見して解決策を講じたり、経営層と現場チームの橋渡し役を務めたりするのも重要な役割です。 PMOで求められるタスクは膨大かつ部門横断的になるため、PMOチーム内では役職ごとに担当範囲や呼称が分かれている場合があります。
| プロジェクトの醍醐味
PM・PMO支援プロジェクトの魅力は、プロジェクトオーナーであるクライアント企業の部門長や役員クラスと直接対話し、高い視座でプロジェクト運営に関与できる点です。計画策定や戦略立案フェーズにおいてクライアントの参謀役として信頼を得て、「あなたのおかげでプロジェクトが成功しました」と感謝の言葉をいただけるようになれば、それ自体が大きなやりがいに直結します。その境地に至るまでは数年間の地道な実績積み上げが必要ですが、プロジェクトの成功を陰で支える縁の下の力持ちとして重要な役割を担っていること自体も、PMOにとって大きなやりがいと言えるでしょう。
【あわせて読みたい】
| IT戦略策定支援案件の特徴は?
| プロジェクトの目的
IT戦略支援プロジェクトの目的は、企業の経営戦略や中期経営計画の目標を達成するために最適なIT戦略を策定することです。ITはあくまで経営目標達成の手段ではありますが、その活用次第では極めて強力な武器となり得ます。したがって、策定されたIT戦略が企業経営に与える影響は非常に大きなものとなります。
| IT戦略策定支援案件が求められている背景
IT戦略支援の案件数は、システム導入やPMO支援のように近年特別急増している分野ではありません。ただし、論理的思考力や幅広く深いIT知識が求められる高度な領域であるため、自社の人材だけでは対応が難しくITコンサルタントに対する需要があります。
| プロジェクトの概要
IT戦略策定支援プロジェクトはシステム開発の実装作業を伴わないため、全体の期間は比較的短期で完了することが多く、概ね3か月程度のプロジェクトが一般的です。また、少数精鋭で遂行される傾向があり、チーム人数は数名規模、場合によってはコンサルタント1名で対応するケースも見受けられます。
| プロジェクトの流れと業務内容
IT戦略策定支援では、IT戦略の策定に加えてシステム導入に先立つ構想策定など経営に近い超上流の業務を幅広く担当します。人員体制はごく少人数で、チームを数名で編成するか、時にはコンサルタント一人で対応する場合もあります。プロジェクトの進行は概ね「現状調査 → 課題分析・対応策の検討 → 経営層への最終報告」という流れです。クライアントと直接ディスカッションする機会が非常に多く、内容も難易度が高いため、経験が浅いうちは議事録作成や会議セッティングなど事務的なタスクが中心となりがちです。このようなプロジェクトでは、まずは地道に下積みを重ねて知見を吸収し、徐々に任される業務範囲を広げていく姿勢が重要となります。
| プロジェクトの醍醐味
IT戦略策定支援プロジェクトの最大の魅力は、扱うテーマがいずれも経営戦略や事業ビジョンに直結しており、企業の将来に大きなインパクトを与えうる点です。クライアント企業のCIOや情報システム部門長など経営層に近い立場の方々と直接やり取りしながらプロジェクトを進めるため、常に高い視座で物事を考え抜くことが求められます。その反面、プロジェクトの難易度は非常に高く責任も重いため、実際には泥臭い作業の積み重ねになる部分も多く、そうしたプレッシャーに耐えうる強い胆力が求められます。しかしだからこそ、IT戦略支援プロジェクトを推進できる人材はシステム導入やPMO支援に比べても圧倒的に希少であり、こういった経験を持つ人は間違いなく重宝されるでしょう。自分を成長させるチャンスがあるなら、ぜひ積極的にチャレンジしてみることをおすすめします。
【あわせて読みたい】
| まとめ
ITコンサルタントが携わるプロジェクトは、超上流の戦略策定から下流のシステム実装まで実に幅広い領域に及びます。自分の強みや志向に合ったキャリアを選択することが、長く活躍していく上で非常に重要です。「キャリアの選択に迷っている」「フリーランスITコンサルの案件についてもっと知りたい」と感じている方は、ぜひ才コネクトへご登録してみてください。
【あわせて読みたい】
 才コネクト
才コネクト