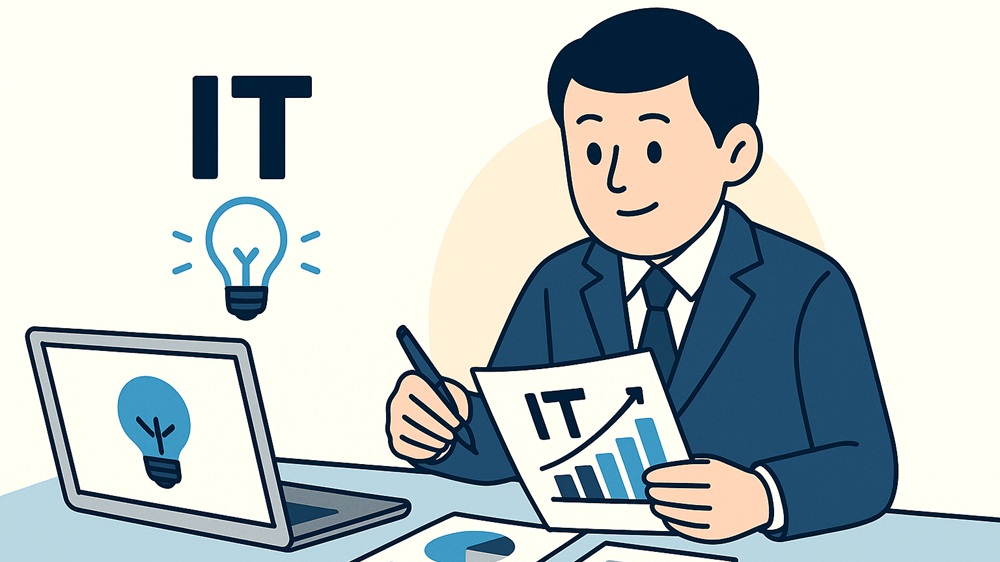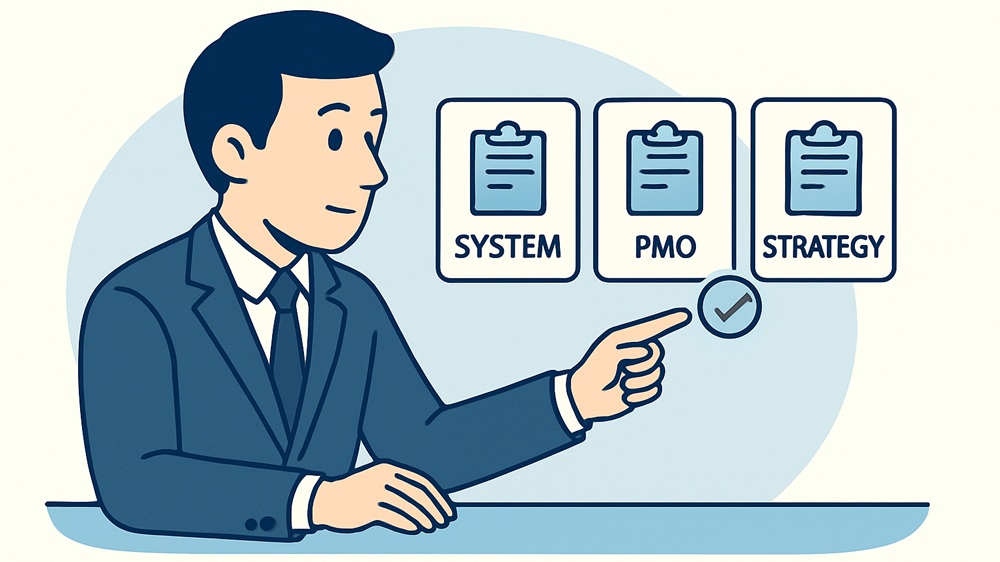コラム
ITコンサルタントが携わるIT構想策定を徹底解説
ITコンサルタントが携わる「IT構想策定」は、プロジェクト成功の土台を築く極めて重要な超上流工程です。なぜなら、IT構想策定によってプロジェクトの方向性やシステム化の目的を明確に定め、関係者全員の共通認識を形成できるからです。例えば、IT構想策定を実施せずに要件定義に入ったプロジェクトでは、「何を実現したいのか」が曖昧なまま進行してしまい、後から大幅な手戻りや追加対応が発生するケースが散見されます。一方、構想策定段階で「Why(なぜ作るのか)」と「What(何を作るのか)」を合意し、ビジネス課題と解決策を整理できていれば、プロジェクト全体がブレない指針を持つことができます。以上の理由から、IT構想策定はITコンサルタントにとってプロジェクトを成功へ導く鍵となる工程と言えるでしょう。
このようにITコンサルが関与するプロジェクトの再上流となるステップでもあるIT構想策定を本記事ではおさらいという意味も含め徹底解説してまいります。
目次
| IT構想策定の定義と目的
IT構想策定とは、業務改革や新システム導入プロジェクトにおける最初の工程を指します。本工程は「システムを作る前にまず何をすべきか」を決める段階であり、プロジェクト全体の基本構想やグランドデザインを描くフェーズです。
構想策定フェーズの目的は、プロジェクトの土台となるシステム化の目的や方向性を明確に定めることにあります。クライアント企業が抱える経営課題や業務上の問題点を経営層・現場双方からヒアリングし、「どのような解決策をITで実現すべきか」「新システムに何を期待するのか」といったポイントを整理・合意します。これにより、プロジェクト全体で共有できる共通の目標(ゴールイメージ)**が設定され、以降の工程で意思決定の軸がぶれにくくなります。
また、IT構想策定では「Why」と「What」──『なぜそのシステムを作る必要があるのか、何を実現するシステムなのか』──を明確化することに重点が置かれます。例えば「自社の売上データがリアルタイムで分析できない」「業務プロセスに属人的なムダが多い」といった課題に対し、「データ統合基盤を構築して経営情報を一元管理する」「業務フローを標準化しERPを刷新する」といった解決策の方向性を示すわけです。
| 構想策定プロジェクトの主要フェーズ
IT構想策定プロジェクトは、いくつかの明確なフェーズに分かれて進行します。典型的には、「現状分析(As-Is)」→「あるべき姿の策定(To-Be)」→「ギャップ分析」→「ロードマップ策定」という流れで検討を深めていきます。以下では、それぞれのフェーズで何を行うかを具体的に解説します。
| 現状分析
最初のステップは、現在の業務プロセスやITシステムの現状を詳細に分析し、問題点や課題を明確化することです。ITコンサルタントは経営層から現場担当者まで幅広くヒアリングを行い、各部門・各階層が感じている不満や非効率のポイントを洗い出します。例えば、「複数システムへの二重入力が発生している」「月初の報告業務に時間がかかり残業が常態化している」「現行システムでは新しい製品情報を管理しきれない」といった声が上がるかもしれません。ヒアリングで得られた断片的な問題意識を整理し、発生している事実とその原因、影響度を分析・裏付けする作業を行います。この段階では、業務フロー図の作成や既存システム構成の可視化を通じて、「どこにボトルネックや課題があるのか」を全体俯瞰し、課題リストとして整理することが一般的です。
| あるべき姿の策定
現状の課題を把握したら、次に理想的な業務フローやITアーキテクチャの姿を描き出します。ここでは経営戦略や今後の事業ビジョンを踏まえ、「将来的に自社はどのような業務運営を目指すのか」「デジタルを活用してどんな競争優位を実現したいのか」を定義します。例えば、事業拡大戦略があるならスケーラビリティの高いシステム基盤が必要でしょうし、顧客体験向上がテーマならCRMやデータ分析基盤の充実があるべき姿に含まれるでしょう。ITコンサルタントはクライアントと共に将来像を議論し、「業務とITのグランドデザイン」を作成します。この中には、解決策となるソリューションアイデアの提示も含まれます。たとえば課題に対して「○○という業務管理システムを導入すれば手作業を80%削減できる」「△△のプロセスを自動化することでヒューマンエラーを防止する」といった具体策を提案し、目指すべき業務プロセスと必要となるシステム機能を描き出します。To-Be像の策定では、全社最適の視点で業務フロー図の将来形やシステム全体像の図解などを作り、経営層にも訴求できるITグランドデザイン資料をまとめることが多いです。
| ギャップ分析と課題解決策の検討
続いて、現状(As-Is)とあるべき姿(To-Be)の差分を洗い出し、解決すべき課題とその優先順位を決定します。現状から理想像までの間には、多くのギャップが存在します。それらを一つ一つ整理し、「何を変えればTo-Beに近づけるのか」「実現のために解決すべき課題はどれか」を特定します。例えば、現状ではデータが部署ごとにサイロ化している一方、To-Beでは全社統合データプラットフォームが必要だとしたら、「データ統合」がギャップ課題になります。また、各部署で別々に使っている業務システムを統合する必要があれば「システム統合」が課題となるでしょう。ギャップごとに解決策の検討も行われます。「自社開発かパッケージ導入か」「クラウドサービス活用かオンプレか」など技術方針もこの段階で議論されます。ただし全てのギャップを一度に解消するのは現実的でない場合も多いため、投資対効果や実現難易度を評価して優先度を付けることが重要です。コンサルタントは経営的観点(費用対効果やROI)と現場観点(現実的な実行可能性)の両面からタスクに順位づけし、「まず着手すべき課題」と「後回しにする課題」を明確化します。ここまでの成果物として、課題解決マップ(課題と対応策の一覧)や実現する機能一覧などが整理されます。
| ロードマップ策定と実行計画
最終フェーズでは、ギャップを埋めるための実行計画を時間軸に沿って策定します。優先度の高い課題から順に、どの順番でどのようなプロジェクトを立ち上げるかを決め、中長期的なロードマップに落とし込みます。例えば、「フェーズ1として基幹システム(ERP)を刷新し、フェーズ2でCRMとデータ分析基盤を構築する。その後フェーズ3でAI活用を本格展開する」というように段階的計画を立てます。ロードマップには各フェーズの目標、スコープ、期間、概算予算などを盛り込み、経営層が判断できる材料とします。またこの段階で、プロジェクト計画書の形で体制案(どの部門から誰が関与するか)、必要予算の年度配分、ベンダー調達計画(いつRFPを出し、いつまでに選定するか)など、実行に向けた具体準備事項も整理します。大切なのは、構想策定で描いた壮大なビジョンを「実行可能なロードマップ」として現実に落とし込むことです。一気にすべてを実現しようとしても組織が追いつかないため、「今回はどこまで実施するか」の線引きを行い、最初のプロジェクトのスコープを明確に定めます。この線引き作業は関係者間の合意形成の場ともなり、「まずはここから始めよう」という経営判断を引き出す重要なプロセスです。ロードマップが策定できれば、IT構想策定フェーズは完了となり、次はいよいよ要件定義など具体的なプロジェクト実行段階へ移行します。
以上がIT構想策定プロジェクトにおける主なフェーズ構成です。これらのステップを経ることで、経営陣から現場担当者までが納得感を持った方針が出来上がります。明確な方針があれば、後で新たな課題が判明した場合でもこの方針に立ち返って柔軟に対応策を検討できますし、多少の環境変化があってもプロジェクトの軸を保つことができます。
| ITコンサルタントの具体的な役割・成果物
IT構想策定プロジェクトにおいて、ITコンサルタントには多岐にわたる役割と成果物の作成が求められます。専門知識とファシリテーションスキルを活かし、クライアント企業の課題整理から将来像の提案まで一貫してリードする立場です。主な役割と成果物を以下にまとめます。
| 課題整理・現状分析のリード
コンサルタントは経営層インタビューや各部署のヒアリングを通じて、現状の問題点を漏れなく洗い出します。ビジネス上の課題をヒアリングシートや課題一覧表に整理し、事実関係や根本原因を分析します。このフェーズでの成果物は、「課題分析レポート」や「As-Is業務フロー図」などです。経営層が抱える経営課題と現場のオペレーション上の課題を紐付けて整理し、課題の全体像を見える化することで、次のステップでの検討材料とします。
| 業務・ITグランドデザインの策定
構想策定の中心となる作業が、あるべき業務プロセスとITアーキテクチャの全体像(グランドデザイン)を描くことです。コンサルタントは業務フローの将来モデルや新システムの概要図、全社的なデータアーキテクチャ図などを作成します。これらはITグランドデザイン資料としてまとめられ、経営陣への提案書・報告書の核となります。グランドデザイン策定には、現行システムの課題を踏まえて新システムで実現すべき機能一覧を作ったり、システム間のインタフェース構成図を描いたりといった具体的作業も含まれます。成果物としては、「業務プロセスの将来姿図」「システム全体構成図」「データ流れ図」などが挙げられます。これにより、経営層はIT戦略の青写真を視覚的に理解でき、プロジェクトにGOサインを出しやすくなります。
| 解決策の提案と優先度付け
コンサルタントは単に現状と理想を分析するだけでなく、具体的なソリューション提案を行う役割も担います。例えば「最新のERPパッケージへの刷新」「RPA導入による定型業務の自動化」「クラウド移行によるシステムコスト削減」といった提案です。各提案について効果見込みや見積コストを試算し、優先度マトリクスなどを用いて実施順序の検討もリードします。これら提案群は、後のロードマップ策定の材料になる「課題対策一覧」「ソリューション比較表」といった成果物にまとめられます。ITコンサルタントは市場のベストプラクティスや最新IT技術にも通じている必要があり、クライアントの課題にマッチした解決策を提示することで付加価値を発揮します。
| ロードマップ・実行計画の立案
前章で述べたロードマップ策定も、コンサルタントの重要な役割です。「何をいつまでに実施するか」を示すロードマップを作成し、経営層の承認を得られる形に整えます。ここではIT投資計画の素案やプロジェクト化のための段取りも提示します。成果物として「ITロードマップ」などが作られます。ロードマップ資料には各フェーズの目的・スコープ・期間・概算コスト・KPIなどが明記され、経営判断と実行準備に資する情報を網羅します。特に予算獲得のための根拠資料として、費用対効果分析や投資回収見通しをまとめるのもコンサルタントの仕事です。
| RFP作成支援・ベンダー選定支援
IT構想策定が完了すると、多くの場合は実際のシステム導入に向けてベンダー選定やソリューション選択のプロセスに移ります。ここでコンサルタントが担うことになるのがRFP作成支援です。構想策定で整理した業務要件やシステム要件をRFPに落とし込み、ベンダー各社が比較検討できるような公平なドキュメントを作成します。また、必要に応じてRFIの段階からベンダーと対話し、適切なベンダー候補を絞り込む支援も行います。RFP発行後は提案内容の評価基準策定やデモのシナリオ作成など、選定プロセス全般でアドバイスと取りまとめ役を担います。成果物として「ベンダー評価レポート」などが一般的です。
以上のように、IT構想策定におけるITコンサルタントの役割は幅広く、戦略策定者でありファシリテーターでありドキュメンテーションのプロでもあります。成果物も経営向けの提案資料から現場向けの分析レポート、詳細な計画書まで多岐にわたります。これらを通じてクライアントに専門性を提供し、プロジェクトの信頼性を高めるのがITコンサルタントの価値と言えるでしょう。
| フリーで活躍するITコンサルが関与する代表的な構想策定案件
IT構想策定は大手コンサルティングファームだけでなく、フリーランスのITコンサルタントにも活躍の場が多い領域です。近年は企業側もプロジェクトごとに専門スキルを持つ個人コンサルタントを起用するケースが増えており、特に以下のようなタイプの構想策定案件はフリーランスが参画しやすい代表例となっています。
| ERP刷新構想プロジェクト
ERP刷新を検討する企業は多く、フリーランスのITコンサルタントにもERP導入構想策定を依頼するケースが目立ちます。例えば、老朽化したレガシーERPからクラウド型ERPへの移行計画策定や、グローバル展開に向けた統一ERP構想などが典型です。こうしたプロジェクトでは、現行業務の課題分析から始まり、新ERPで実現すべき要件定義、複数ERPパッケージの比較検討、ロードマップ策定まで一連の構想策定を行います。多くの企業が基幹システム再構築に乗り出しているため、ERP刷新構想のニーズは非常に高いです。フリーランスコンサルタントは特定のERP製品(SAPやOracle、Microsoft Dynamicsなど)に精通している強みを活かし、業務プロセス標準化とシステム要件定義をリードし、最適なERPソリューション選定支援を行うことが求められます。
| 業務改革伴走型の構想策定
単発のシステム導入に留まらず、企業のBPRを中長期で伴走支援するタイプの案件もあります。例えば、「販売管理業務のDX推進構想」「バックオフィス業務効率化プロジェクト」など、テーマごとにコンサルタントが入り込み、構想策定から実行フェーズまで並走するケースです。フリーランスのITコンサルタントは特定領域(会計、サプライチェーン、人事など)の業務知識とIT知見を買われ、準PM的な立場で関与します。まず構想策定フェーズで課題を洗い出し改革プランを描き、その後の実行段階(システム導入や業務変更)でもアドバイザーないしPMOとして支援を続けます。このような案件では、現場密着で部門担当者とコミュニケーションをとりながら進めるため、社内メンバーに近い視点で動けるフリーランスの強みが発揮されます。成果物としては初期に「業務改革ロードマップ」や「ツール選定方針書」を作成し、その後は各施策の推進計画や効果検証レポートなどを都度まとめていきます。企業にとってはスポット的な助言ではなく腹付添い型のコンサルを得られるメリットがあり、フリーランスにとっては自身の経験を長期的改革に活かせるやりがいのある案件です。
| 全社IT最適化構想プロジェクト
企業全体のIT資産を見直し、全社横断的なIT最適化計画を策定する大型案件も、フリーのコンサルタントが起用されることがあります。たとえば「グループ会社統合に伴うシステム全体最適化構想」「ITコスト削減のためのアプリケーションポートフォリオ見直し計画策定」などです。こうしたプロジェクトでは、既存システム群の現状調査から着手し、重複システムや非効率なIT投資を洗い出します。その上で将来の全社アーキテクチャをデザインし、どのシステムを残しどれを刷新・統合するか、クラウド移行するかといった方針を立てていきます。ITグランドデザイン策定コンサルティングと呼ばれるサービス領域であり、広範な知識と分析力が要求されますが、特定の業界や技術に詳しいフリーランスコンサルタントが抜擢されることも少なくありません。成果物は「IT投資マスタープラン」「統合システム構成図」「段階的移行計画書」など多岐にわたります。経営戦略とIT戦略を整合させ、部分最適ではなく全体最適を図る視点が重要になるため、第三者の客観的立場で組織横断の調整を進められる外部コンサルタントの価値が大きい案件です。フリーランスとして参画する場合も、CIO補佐的なポジションで経営陣と直接協議しながらプランを練り上げていくため、非常にチャレンジングですが実績になれば信頼と評価を得られるでしょう。
以上がフリーランスITコンサルタントが関与する代表的な構想策定案件の例です。これら以外にも、DX戦略策定や新規事業立ち上げに伴うIT構想など、幅広いテーマで構想策定のニーズがあります。フリーランスにとって重要なのは、自身の得意分野や業界知識を活かせる案件を選び、的確な成果物を残すことで次の仕事への信頼に繋げることです。
| 最新のIT構想策定トレンド:生成AI時代の戦略立案
IT構想策定の手法や内容も、時代の変化とともに進化しています。特に昨今は生成AIの台頭やDXの加速を背景に、新たなトレンドが生まれています。ここでは「AI活用前提のIT戦略」「生成AIによる要件収集・分析支援」「デジタル人材戦略との接続」というキーワードを軸に、最新の傾向を見てみましょう。
| AI活用前提のIT戦略策定
かつてはIT戦略といえば基幹系システム刷新や業務効率化が中心でしたが、今やAI技術を前提に組み込んだIT構想が主流になりつつあります。例えば、販売戦略にAIによる需要予測モデルを組み込んだり、顧客対応にAIチャットボットを活用する前提でシステム全体を設計したりといった具合です。IT構想策定の段階で「この業務領域には機械学習モデルを導入して自動化率を高める」「生成AIで自動生成されるレポートを経営判断に役立てる」といったAI活用シナリオが描かれます。これは単なる思いつきではなく、経営戦略上もAIが競争力のカギとなっているためです。生成AI戦略なくして企業の成長戦略は描けないとも言われ、特に2023年以降、経営陣から「うちも生成AIをどうにか活用できないか?」との声が上がるケースが激増しています。ITコンサルタントとしては、AIの技術動向や具体的なユースケースを把握した上で、クライアントのビジネスに応じたAI導入ロードマップを提案することが求められます。例えば製造業の構想策定では「工場IoTとAI分析で予知保全を実現する」、金融業では「顧客データをAI解析しパーソナライズ提案を強化する」など、業界ごとのAI活用戦略を盛り込むのです。また、コンサルファーム各社もAIを前提としたビジネス変革支援サービスを競うように展開しており、構想策定サービス自体にAIの視点が組み込まれるのが当たり前になってきています。つまり「AI時代のITグランドデザイン」を描けることが、現代のITコンサルタントの重要なスキルセットの一部となりつつあるのです。
| 生成AIによる要件収集・分析支援
構想策定プロジェクトの進め方にも、生成AIツールが活用され始めています。たとえば、ヒアリング内容の整理や大量のテキスト資料の分析にChatGPTのような生成AIを使うケースです。コンサルタントが何十人ものステークホルダーから聞き取った要望や課題をテキスト化した場合、その膨大なメモをAIにかけて共通するキーワードの抽出や意見のクラスタリングを自動化できます。また、市場調査レポートや専門記事など外部情報を収集して構想に活かす際にも、生成AIが要約や論点整理を手伝ってくれます。さらに、ドキュメント作成支援も見逃せません。例えば構想策定の提案書ドラフトをAIに生成させ、人間がブラッシュアップするといった方法です。従来はコンサルタントが数日にわたり練っていた文章案を、AIが数分で叩き台を出してくれることで、生産性が飛躍的に向上する場面も増えています。一部の先進企業では、自社データを組み込んだ専用のAIアシスタントを導入し、要件定義書やRFPの初稿をAIに作らせている例もあります。もちろん生成AIの活用には注意点もあります。機密情報を扱う場合の情報漏洩リスクや、AIの回答精度の検証責任など、人間のチェックは不可欠です。しかしそれでも、分析作業や資料作成のスピードが飛躍的に上がる利点は魅力的です。IT構想策定においてコンサルタントは、本来クライアントとの議論や提案の質向上に時間を割きたいものです。生成AIに定型的な分析・整理作業を任せることで、人間はより付加価値の高い思考に集中できるようになります。今後は「AIと協働しながら構想策定を行う」のが当たり前になり、AIリテラシーの高いコンサルタントほど早く正確に構想策定を進められるようになるでしょう。例えば、エクセルの自由記述データをAIで集計・可視化したり、議事録からアクションアイテムを抽出したりといった支援も考えられます。これらはいずれも構想策定の効率と網羅性を高める方向で働き、結果的により質の高いIT戦略を短期間で策定する助けとなっています。
このように、IT構想策定は常に最新のビジネストレンドやテクノロジー動向を取り入れながら進める必要があります。常に学び、進化する姿勢で最新トレンドをキャッチアップし、クライアントに提供価値として還元していくことが大切です。
| まとめ
いかがだったでしょうか?
記事全体を通じて、「ITコンサルタントが関与するプロジェクトにおけるIT構想策定」とは何か、その定義・目的からプロセス、役割、具体例、そして最新トレンドまでを包括的に見てきました。結論として改めて強調したいのは、IT構想策定はプロジェクト成功の可否を握る極めて重要な工程であり、ここでの働きこそがITコンサルタントの真価を示す場であるということです。
フリーランスであれ所属コンサルタントであれ、IT構想策定に携わることは大きな挑戦であり同時に成長の機会です。結論として、IT構想策定とは「ITでビジネスをどう変革するか」を描き切ることであり、その実践を通じてITコンサルタントはクライアントの未来を共に創る真のパートナーとなれるのです。上流工程のこのステージで発揮された価値は、プロジェクト成功という成果となって現れ、コンサルタント自身の評価と信頼につながっていくでしょう。ぜひ本記事の内容を踏まえ、次なるプロジェクトで実践的に活用してみてください。
IT構想策定関連の案件をお探しの方、フリーで働くITコンサルタントのための案件紹介プラットフォーム、才コネクトへのご登録も併せてご検討ください。
 才コネクト
才コネクト