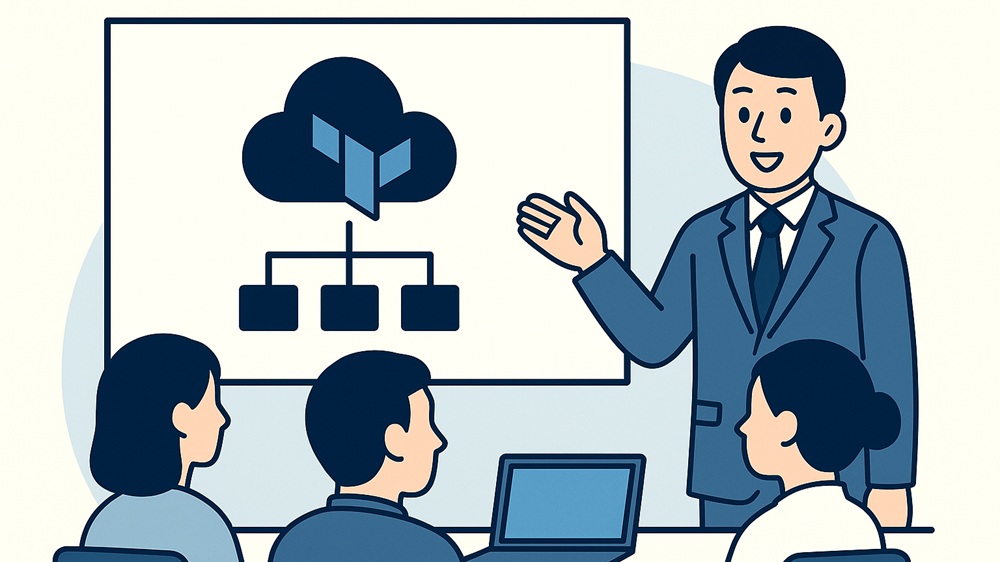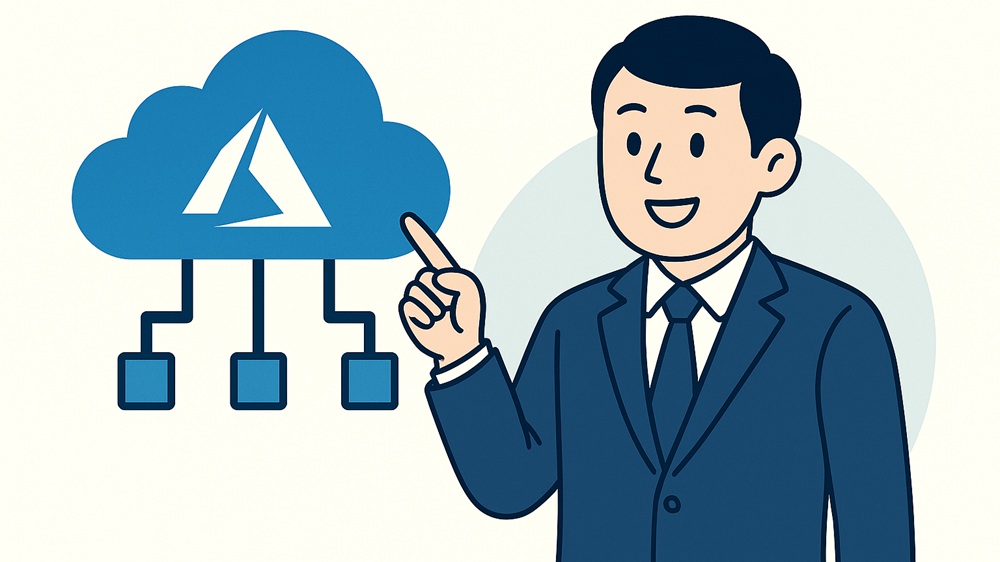コラム
Snowflakeとは?クラウドDWHの特徴・メリット等を徹底解説
Snowflakeは近年注目を集めるクラウド型のデータプラットフォーム(クラウドDWH)です。Snowflakeを活用すれば企業のデータ基盤は強化され、ビッグデータの利活用が容易になります。Snowflakeが従来のデータウェアハウス(DWH)では難しかった柔軟なスケーラビリティとシンプルな運用性を実現しているためです。例えばSnowflakeなら複数部門が同時に大量データを分析してもリソース競合が起きず、必要な時に必要な分だけコンピューティングリソースを追加でき、無駄なコストも抑制可能です。よって、クラウドDWHであるSnowflakeは企業のデータ活用を加速し、競争力強化につながる強力なソリューションとなります。
目次
| Snowflakeとは?
Snowflake(スノーフレーク)は、クラウド上で提供されるDWHサービスとして2014年に誕生しました。従来はオンプレミスでサーバーやストレージを自社管理する必要がありましたが、Snowflakeではインフラ管理が一切不要なSaaS型のデータプラットフォームとなっています。現在では単なるDWHの枠を超え、データの蓄積(データレイク)から高度な分析・他社とのデータ共有までを包括的に行える「クラウドデータ基盤」へと進化しています。主要クラウド(AWS、Azure、GCP)上で動作し、マルチクラウド環境にも対応しているため、自社のクラウド戦略に合わせてSnowflakeを活用できます。
Snowflake最大の特長は、高度なパフォーマンスとスケーラビリティです。従来のオンプレミス型DWHはハードウェア増強にコストと時間がかかり、需要変化への追随が困難でした。一方、Snowflakeは必要なときに必要なだけリソースをスケールアップ/アウトでき、利用しないときはリソースを停止してコストを抑えることが可能です。この柔軟な従量課金モデルにより、小規模から大規模まで効率的に運用できる点が評価されています。
| Snowflakeの特徴
Snowflakeが他のデータ基盤と一線を画す主な特徴を整理します。
| 完全マネージドサービス
Snowflakeはクラウド上のフルマネージドサービスであり、ユーザー企業はサーバー管理やソフトウェアアップデート、障害対応などのインフラ管理から解放されます。必要なのはデータのロードとクエリ実行だけで、スケーリングやメンテナンスは自動で処理されます。
| ストレージとコンピュートの分離
Snowflakeはデータを保存するストレージ層と、クエリ処理を行うコンピュート層(仮想ウェアハウス)を完全に分離したアーキテクチャを採用しています。この設計により、複数のコンピュートリソースが同一のデータに同時アクセスしても相互に競合せず、ワークロードごとに独立したパフォーマンスを発揮できます。
| マルチクラウド対応
SnowflakeはAWS、Azure、Google Cloudといった主要クラウドプラットフォーム上で提供されており、クラウド間のデータ統合や移行を容易にします。異なるクラウド環境にまたがるデータをSnowflakeで一元管理することで、ハイブリッド/マルチクラウドのデータハブとして機能させることが可能です。
| 柔軟な従量課金とコスト最適化
従来のDWHはサーバを起動し続けるだけでコストが発生しましたが、Snowflakeは使うときだけコンピュート費用がかかる真の従量課金モデルともいわれています。ウェアハウス(コンピュート)リソースは自動休止と必要時の自動再開が可能で、複数のウェアハウスを用途別に使い分けることで無駄なコストを削減できます。ストレージ料金とコンピュート料金が分離しているため、データ保存自体のコストも安価に抑えられます。
| 充実したセキュリティとガバナンス
エンタープライズ向けに必要な認証・暗号化・アクセス制御機能が網羅されています。シングルサインオンや多要素認証に対応し、保存データは常時暗号化されます。マスキングやトークン化による機微情報保護、行レベルのアクセスコントロール、細かなロール権限設定が可能で、安全なデータ活用と共有を両立できます。
| Snowflakeのアーキテクチャ
Snowflakeの優れた性能を支えるのが、その独自のアーキテクチャです。Snowflakeは従来のDWHで採用されていた「シェアードディスク」や「シェアードナッシング」といったアーキテクチャの課題を克服するため、マルチクラスター・シェアードデータ(Multi-Cluster Shared Data)方式を導入しています。
このアーキテクチャでは、大きく分けて以下の3つの層で構成されています。
| ストレージ層
テーブルなどのデータはクラウド上のオブジェクトストレージ(AWSならS3、AzureならBlob Storageなど)に保存されます。Snowflakeはデータを自動的に圧縮・最適化して格納するため、ユーザーがストレージ容量を気にする必要はありません。ほぼ無制限のデータ蓄積が可能で、スケールに応じて自動で容量拡張されます。
| コンピューティング層(仮想ウェアハウス)
クエリ実行を担う計算リソースの集合です。Snowflakeではユーザーが任意に仮想ウェアハウスを作成し、そのサイズ(性能)をXSから3XL以上まで選択できます。仮想ウェアハウスはストレージ上のデータを読み書きしますが、自身はデータを保持せずCPUとメモリによる計算処理に特化します。複数の仮想ウェアハウスが同じデータを扱う場合でも、各ウェアハウスは独立して動作するため、互いの処理が干渉しません。必要に応じてクラスター数を自動で増減させるオートスケール機能もあり、同時実行クエリ数に応じて処理能力を柔軟に拡張できます。
| クラウドサービス層
Snowflake全体を統括する制御層です。ユーザーからのクエリを解析・最適化し、各ウェアハウスに振り分けるクエリ最適化エンジンや、認証・アクセス制御、メタデータ管理などを担います。この層がSnowflakeの“頭脳”に相当し、全体の調整役として機能します。
これらの層を分離したSnowflake独自の設計により、ストレージ容量の増大やクエリ負荷の急増にも即座に対応でき、従来型DWHで問題となっていたリソース不足や性能劣化を回避できます。
| Snowflakeのメリット・デメリット
以上を踏まえ、Snowflakeを導入することによって得られる代表的なメリットを整理します。
| メリット
| スケーラビリティとパフォーマンス向上
必要なときに必要なだけリソースを追加できるため、突発的な分析需要にも即応できます。複数部門・チームが同時にデータ分析を行っても、仮想ウェアハウスを分ければ性能低下なく処理可能です。従来のようにピークに合わせた過剰投資や、リソース競合による待ち時間が解消され、ビジネスのスピードに合わせたデータ活用が実現します。
| 運用負荷の大幅軽減
ハードウェア管理やソフトウェア更新作業が不要なため、システム管理者の負担が減ります。さらにSnowflake独自のタイムトラベルやゼロコピークローン機能により、データ復元や環境コピーが瞬時に行えるため、バックアップ・検証作業も簡易になります。パフォーマンスチューニングも自動化されており、極端なケースを除き専門的なDBチューニング作業がほぼ不要です。
| コスト最適化と柔軟な料金モデル
Snowflakeは完全な従量課金のため、使った分に対してのみコストが発生します。利用が少ない期間は自動でコンピュートが停止し費用が抑えられる一方、必要時には大規模リソースを一時的に割り当てて処理時間を短縮するなど、コストと時間のトレードオフを柔軟に選択できます。ストレージと計算リソースの課金が分離している点も効率的で、安価なクラウドストレージに大量のデータを蓄積しつつ、計算コストは効率よくコントロール可能です。
| データ統合と共有の容易さ
Snowflake導入により、企業内外のデータ統合が格段に容易になります。単一のプラットフォーム上でデータレイク的な生データ保存から、DWHとしての集約・加工、さらにはデータマートとしての提供まで一貫して実現できるため、異なるシステム間でデータを受け渡す手間やタイムラグが減少します。他部門やパートナー企業とのデータ共有もセキュアに行えるため、データを軸としたコラボレーションや新たな価値創出が促進されます。
| デメリット
一方で、Snowflake導入にあたって留意すべきデメリットや課題も存在します。主なものを挙げます。
| 大量利用時のコスト増リスク
Snowflakeは使った分だけ課金されるモデルですが、大量データを頻繁に処理するケースではコストが増大する可能性があります。特に大規模なクエリを繰り返し実行したり、常時大型の仮想ウェアハウスを起動し続けたりすると、従来の固定課金型DWH以上に費用がかさむ場合もあります。適切なクエリ最適化やスケジューリング、省リソース設定によるコスト管理が不可欠です。
| 既存システムからの移行負荷
オンプレミスのDWHや他のデータベースからSnowflakeへ移行する際には、データスキーマの変換やデータクレンジングが必要になるケースがあります。また、ネットワーク帯域の違いから大量データ転送に時間を要するなど、移行プロジェクトには入念な計画策定と段階的な移行が求められます。移行期間中は両システムの併用やデータ整合性の確保など、ITコンサルタントの支援が重要となるでしょう。
| 運用管理やコストモニタリングの必要性
Snowflakeは自動運用機能が豊富ですが、導入すれば全く手放しというわけではありません。従量課金ゆえに、どの部門・ユーザーがどれだけリソースを消費しているかをモニタリングし、不要な処理があればクエリ改善やリソース制限を行うなどガバナンスが重要です。運用開始後も定期的な利用状況のレビューや、費用対効果の分析が必要で、これを怠ると思わぬコスト増やパフォーマンス低下を招く可能性があります。
| 他システムとの統合に専門知識が必要
Snowflake自体は豊富なAPIやコネクタを提供し、多様なETLツール・BIツールと連携可能です。しかし、自社の既存業務システムやデータパイプラインにSnowflakeを組み込むには、適切な設計と専門知識が求められます。特にリアルタイム連携や機械学習基盤との接続など、高度な統合を図る場合、最適なデータフローやアーキテクチャを検討しないとシステムが複雑化する恐れがあります。SnowflakeはAI/ML機能も拡充しつつありますが、本格的な機械学習ワークロードについては別途専用ツールとの連携が前提となる点も考慮が必要です。
| SnowflakeとRedshift/BigQueryの違い
Snowflakeとよく比較される代表的なクラウドDWHサービスに、Amazon Redshift(AWS)とGoogle BigQuery(GCP)があります。各サービスのアーキテクチャや特徴には違いがあり、用途や環境によって適性が異なります。
| アーキテクチャの違い
Redshiftはクラスターノードを構成してスケールする仕組みで、従来型のシェアードナッシングアーキテクチャを採用しています。ノード追加で性能向上が図れますが、一部操作ではダウンタイムが発生する場合もあります。Snowflakeは上述の通りストレージとコンピュート分離型で、必要に応じてコンピュートクラスターを増減できます。BigQueryはサーバーレスアーキテクチャで、ユーザーがインフラを意識せずにクエリを投げるだけで自動的にバックエンドがスケールします。
| コストモデル
Redshiftはクラスター(ノード)単位の固定課金が基本で、リザーブドインスタンスを活用することで長期的にはコストを抑えやすいモデルです。常時稼働させて重い処理を行う場合にコストメリットがあります。Snowflakeはストレージとコンピュート完全分離の従量課金で、利用時間・量に応じた課金です。必要最小限のリソースで済ませれば低コストですが、使い方次第で増減します。BigQueryはクエリ実行ごとにデータスキャン量等で課金されるモデルで、使わなければほぼ無料に近いコストに抑えられる反面、大量クエリ実行時には費用が跳ね上がる可能性があります。
| サービス統合とエコシステム
RedshiftはAWS、BigQueryはGCPの各種クラウドサービスと密接に統合されており、Snowflakeはマルチクラウド対応と豊富なサードパーティ連携による柔軟性が特長です。ただしネイティブサービス連携の容易さでは、特定クラウド専用のRedshiftやBigQueryに分がある場面もあります。
まとめると、AWS環境中心でDWHを構築するならRedshift、GCP上でサーバーレスDWHが必要ならBigQuery、マルチクラウド戦略や徹底したリソース分離による柔軟性を求めるならSnowflake、といった使い分けが考えられます。それぞれのサービスに強みがあるため、自社の要件(データ量、既存環境、予算、運用方針など)に合わせて選定することが重要です。
| Snowflakeの導入ユースケース
Snowflakeはさまざまな企業・用途で活用が進んでいます。代表的な導入ユースケースを紹介します。
| データ分析基盤の新規構築・刷新
クラウド上に新たな分析基盤(データ基盤)を構築するケースや、部門ごとに分散していたデータマートを統合し全社横断のDWHに再構築するケースです。従来オンプレDWHをSnowflakeに移行し、スケーラビリティ向上とコスト削減を実現する例も増えています。
| マーケティングプラットフォームへの活用
マーケティング領域のデータ基盤としてSnowflakeを用いるケースです。顧客データや行動ログをSnowflakeに集約し、CDPやマーケティングオートメーションツールと連携することで、高度な分析とパーソナライズを実現できます。
| データのエクスチェンジとマネタイズ
自社データを匿名加工してSnowflakeマーケットプレイスで共有・販売し、新たな価値創出や収益源とするケースです。他社データを取り込んで分析に活用することもSnowflakeなら容易です。
| ITコンサルタントが関与しうるSnowflake関連プロジェクト
最後に、Snowflakeに関連してITコンサルタントが支援できるプロジェクトの種類を整理します。Snowflake導入・活用の各フェーズで、専門知識を持つコンサルタントの支援機会がねむっています。
| 導入計画・PoC・環境構築支援
Snowflake採用の初期検討から本番環境構築まで一貫して支援します。現状システムの課題分析からPoC(概念実証)による性能・コスト検証を経て、本番導入ではデータパイプライン整備やセキュリティ設定、他システムとの接続連携までサポートします。
| 移行プロジェクト支援
既存のオンプレミスDWHや他クラウドDWHからSnowflakeへの移行を推進します。データスキーマ変換やETL再構築、並行運用計画の策定など多岐にわたるタスクを専門家の立場でリードし、大規模移行でも綿密な計画とテストによりスムーズなシステム切替を支援します。
| 定着化支援(ユーザー教育・運用定義)
Snowflake導入後、そのプラットフォームが社内で定着するようユーザー教育や運用ルール整備、利用状況のモニタリングなどを通じて定着化を後押しします。
| 分析活用・BI導入支援
Snowflake上のデータ活用を推進します。BIツールの選定・ダッシュボード構築からデータ分析コンサルティングまで、データに基づく意思決定を支援します。
| まとめ
いかがだったでしょうか。
以上、Snowflakeとは何か、その特徴や仕組み、メリット・デメリット、競合サービスとの違い、そして活用事例やコンサルタントの関与領域まで包括的に解説しました。Snowflakeはクラウド時代における先進的なデータ基盤であり、適切に導入・運用すればデータ活用の可能性を大きく広げてくれることになるため、DX時代においてはクライアントとしても価値あるSLといえそうです。そのため今後、Snowflakeに知見・ナレッジのあるITコンサルタントの需要はますます高まってくることが予想されます。
Snowflake関連の案件をお探しの方、フリーで働くITコンサルタントのための案件紹介プラットフォーム、才コネクトへのご登録も併せてご検討ください。
【あわせて読みたい】
 才コネクト
才コネクト